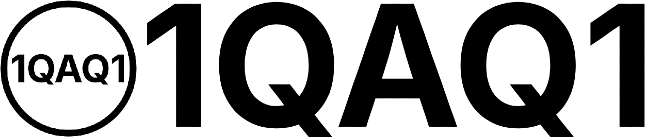今日は回鍋肉(ホイコーロー)定食を食べてきた。普段は自炊派の私だが、今日は残業で疲れていたので、駅前の中華料理店に立ち寄ることにした。
キャベツと豚肉が程よい味付けで、油っこさも気にならない。ホッとする味だった。スマートフォンを取り出してSNSに投稿しようとした時、見知らぬ番号からメッセージが届いた。
「1QAQ1」
意味不明な文字列だ。スパムかと思ったが、なぜかその文字列に見覚えがある気がした。頭の片隅で何かが引っかかる。
家に帰ってからも気になって仕方がなかった。パソコンを開いて検索してみたが、まったくヒットしない。布団に入ってからも、その文字列が頭から離れなかった。
翌朝、会社に向かう電車の中で突然思い出した。10年前、高校の同級生だった田中が、卒業式の日に私に渡した暗号だ。「いつか必要になる時が来たら、これを思い出して」と言っていた。
田中は在学中、いつも不思議な言動が多かった。UFOや超能力、都市伝説に詳しく、よく私に話してくれたものだ。正直、その頃の私は少し引いていた。でも、優しい性格で、困っている人を見かけると必ず手を差し伸べる人だった。
卒業後、田中とは連絡を取っていない。SNSでも見つからなかった。そう言えば、最近地元のニュースで、謎の失踪事件が増えているという話を聞いた。
仕事中も落ち着かず、昼休みに近所のカフェで一人考え込んでいた時、また同じ番号からメッセージが届いた。
「覚えていましたか?今夜8時、母校の裏門で待っています。来られるなら、この暗号の意味を教えます。でも、来ないほうがいいかもしれません。選択はあなたの自由です。」
確かに田中の言い回しだ。胸が高鳴る。これは行くべきなのか?普通に考えれば、怪しすぎる。でも、もし本当に田中からのメッセージなら?失踪事件との関連は?頭の中がグルグル回る。昼食に食べたサンドイッチが胃の中で重たく感じる。
「課長、少し早めに失礼していいですか?」 声が震えているのが自分でもわかった。課長は意外にもあっさりと頷いてくれた。きっと顔色が悪かったのだろう。
仕事を終え、まだ明るい外を見上げた。夏の夕暮れは長い。母校まで歩いて30分。行けば何かが変わる予感がする。でも、それは良い方向への変化なのだろうか。汗ばむ手のひらをハンカチで拭う。駅前の雑踏を歩きながら、高校時代の記憶が次々と蘇ってくる。
田中は確かに変わっていた。でも、悪い意味では全然なかった。むしろ、周りの空気を読みすぎて窮屈そうにしている私たちの方が不自然だったのかもしれない。彼は自分の興味のあることを純粋に追求していた。今の私にはそんな純粋さは残っているだろうか。
ポケットの中のスマートフォンが震える。また新しいメッセージだ。開くのが怖い。でも、この謎を解かずにいられない。深呼吸して、画面を見つめた。手が震えて、一度ロック解除に失敗する。
「まだ迷っているでしょう?」
ゾクッとした。見られているのだろうか。慌てて周囲を見回すが、帰宅途中のサラリーマンと学生たちが行き交うだけだ。太陽はまだ地平線に届いていないが、空は少しずつオレンジ色に染まりはじめている。
続けて、もう一通メッセージが届く。
「1QAQ1。この暗号には、あの日あなたが教えてくれた大切なことが込められています。覚えていませんか?」
あの日?頭を抱えて考え込む。近くのコンビニの前にしゃがみ込んでしまった。店員が不審そうな目で見ている。でも、そんなことは気にしている場合じゃない。何か、大事なことを忘れている。というか、忘れたくて忘れたことがあるような気がする。
田中が卒業式の日、私に暗号を渡した時の表情。笑顔だったけど、どこか寂しそうで、そして決意に満ちていた。その直前、私は田中に何を話したんだろう。
スマートフォンの画面が再び明るくなる。
「時間です。このままここで考え続けますか?それとも、真実を知りにきますか?」
足が勝手に動き出していた。母校への道を、私は歩き始めていた。靴が擦れて足首が痛い。コンビニで買った水のペットボトルが、歩くたびにカバンの中で揺れている。
日が傾き始め、街灯が一斉に点灯した。母校の古い校舎が、夕暮れに浮かび上がってくる。そこはまるで、時間が止まったままのようだった。

裏門に近づくと、懐かしい錆びた金属の匂いが鼻をつく。かつては毎日くぐっていた門。でも今は、なんだかとても遠い昔のことのように感じる。
まだ誰もいない。
木々の間を風が抜けていく音が、どことなく不気味だ。スマートフォンを確認すると、電波が弱くなっている。ここは確かに電波が入りづらい場所だった。
「来てくれたんですね」
突然、後ろから声がした。振り向くと、そこには確かに田中がいた。でも、なんというか、少し違う。同じ顔なのに、まるで別人のようだ。
「久しぶり…」 声が震える。相手が本当に田中なのか、まだ確信が持てない。
「覚えてますか?卒業式の日のこと」 田中はまっすぐに私の目を見つめてくる。
「正直、あまり…」
「そうですよね。でも、あの日あなたは、私に大切なことを教えてくれたんです。『人は誰でも、自分の信じる道を歩んでいい。たとえそれが、他の人には理解できなくても』って」
その瞬間、記憶が急に蘇ってきた。そうだ。卒業式の後、田中が超常現象の研究者になりたいと打ち明けてきた時、私はそう言ったんだ。でも、その時の私は本気で言ったわけじゃない。ただ、泣きそうな顔をしている友達を慰めたかっただけ。
「その言葉が、私の人生を変えました」 田中は懐から古ぼけた手帳を取り出した。
「1QAQ1。これは私たちの学校の図書館の分類番号なんです。超常現象に関する本が置いてあった棚。あなたのその言葉がなければ、私は自分の道を諦めていたかもしれない」
私の中で何かが込み上げてきた。申し訳なさ?後悔?それとも安堵?
「実は、私たちは見つけてしまったんです。何かを」 田中の表情が急に深刻になる。
「この町で起きている失踪事件。あれは…」
その時、急に辺りの空気が変わった。街灯が一瞬激しく明滅する。田中の顔が青ざめる。
「もう来てしまった。話すのが長すぎた」 田中は私の手を強く握る。手が冷たい。
「あなたには関わってほしくなかった。でも、もう遅い。1QAQ1。この暗号には、もう一つ意味があるんです。『一度に尋ねる一つの質問』。今夜、あなたは選択を迫られます」
突然、背後から強い光が差し込んできた。振り向こうとする私の肩を、田中がぐっと掴む。
目を閉じた瞬間、強烈な風が吹き抜けた。耳鳴りがする。それとも、これは耳鳴りではない何かか。体が浮くような、奇妙な感覚。
「まだ目を開けないで!」 田中の声が遠くなったり近くなったりする。
何かが起きている。確実に、何かが起きている。でも、それが何なのかを理解する勇気が出ない。今、目を開けてしまったら、もう後戻りはできないような気がした。
そういえば、今朝食べた回鍋肉定食のことを考える。なんでこんな時にそんなことを?でも、あの何でもない日常の味が、今はやけに恋しい。
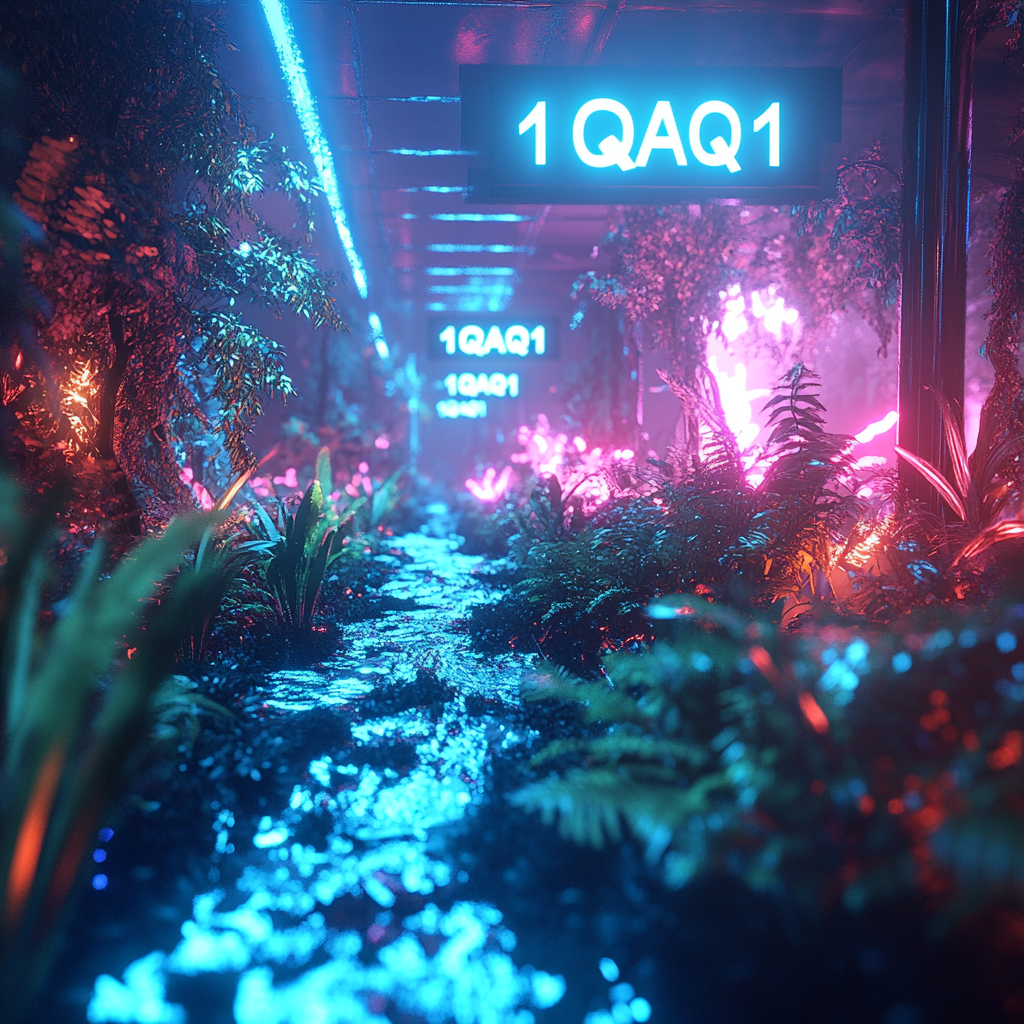
「もう、大丈夫です」
目を開けると、そこはもう学校の裏門前ではなかった。かすかに蛍光する植物らしきものに囲まれた空間。天井も床も壁もない。いや、あるのかもしれないが、目が捉えられない。
「ここが、私たちの研究所です」 田中が申し訳なさそうな表情を浮かべる。
「研究所?」 自分の声が、妙に空虚に響く。
「はい。10年前から、私たちはここで研究を続けています。この町で起きている失踪事件。あれは事件ではありません。この場所に、意図せず迷い込んでしまう人たちがいるんです」
「じゃあ、その人たちは…」
「無事です。ここには時間が存在しません。だから、表の世界では失踪として扱われる。でも、私たちにはそれを防ぐ手段がある。それには…」
田中の声が途切れる。遠くで何かが明滅しているのが見える。
「あなたの力が必要なんです」
「私の…力?」
「はい。あの時の言葉を、本当の意味で」
突然、頭の中に映像が流れ込んでくる。卒業式の日。泣きそうな顔で夢を語る田中。軽い気持ちでかけた言葉。でも、その言葉は本当は、私自身に向けたものだったのかもしれない。
「選択をしてください」 田中が私の目をまっすぐ見つめる。
「ここに残り、私たちと共に研究を続けるか。それとも、全てを忘れて日常に戻るか」
また強い光が差し込んでくる。今度は正面から。
「でも、急いで決める必要はありません。この場所には時間がないと言いましたよね」 田中が微笑む。
私は深いため息をつく。今朝の回鍋肉の味を思い出す。日常とは、そういうものだ。でも、もし…
「その前に、聞かせてほしい」 私は口を開く。
「本当に、私にしかできないの?」
田中の表情が複雑に歪む。
「本当に…私じゃなきゃダメなの?」 自分でも驚くほど冷静な声が出た。
田中は黙ってうつむく。その沈黙が、何かを物語っていた。
「正直に答えてほしい」
「…いいえ」 田中の声は小さかった。
「あなたでなくてもいい。でも、私が選んだんです。あの日の言葉を贈ってくれた人を。ただそれだけ」
なんだか急に疲れが出てきた。今朝から今までのことが、走馬灯のように頭の中を駆け巡る。回鍋肉定食を食べて、謎のメッセージが来て、そして今、こんな現実離れした場所にいる。
「他の失踪者は?」
「みんな、自分の意思で戻っていきました。記憶を消して」 田中は遠くを見つめながら答える。
「私たちは研究者として、観測者としてここに残る。それが使命だと信じている。でも、その選択を他人に強いる権利は私たちにはない」
蛍光する植物らしきものが、そよ風で揺れている。風?ここには風があるのか?それとも、これも何か別の現象なのか。
「田中さん」 私は親しみを込めて呼びかけた。
「あの時の言葉は、確かに軽い気持ちで言ったかもしれない。でも、今なら分かる。あれは嘘じゃなかった」
田中の目が少し潤んだように見えた。
「だからこそ、私は戻る。戻って、自分の信じる道を歩みたい。それが、あの時の言葉に一番ふさわしい答えだと思うから」
「そう…ですね」 田中は柔らかな笑顔を浮かべた。
「実は、私もそう願っていました」
強い光が、また部屋を満たし始める。
「では、これを」 田中が一枚の紙を差し出す。
「もし、どうしても必要になった時は、この数字を」
その時、全ての光が一瞬に収束した。目を開けると、そこは学校の裏門前。夜の闇が深く、街灯だけが静かに辺りを照らしている。
手の中には一枚の紙。そこには「1QAQ1」の文字と、もう一つの数列が書かれていた。
翌朝、会社の自分のデスクで目が覚めた。残業で疲れて、そのまま寝てしまったのだろうか。
机の上には、昨日食べた回鍋肉定食の領収書。ポケットに手を入れると、一枚の紙。でも、そこに書かれた文字は、まるで読めない言語のように見える。不思議と焦りはなかった。いつか、必要な時が来たら読めるような気がした。
窓の外では、いつもと変わらない朝日が昇っていく。今日も、どこかで誰かが、自分の信じる道を歩き始めているのかもしれない。
そう思うと、急に昨日食べた回鍋肉の味が懐かしく感じられた。今度は自分で作ってみようかな。そんなことを考えながら、新しい一日が始まっていく。